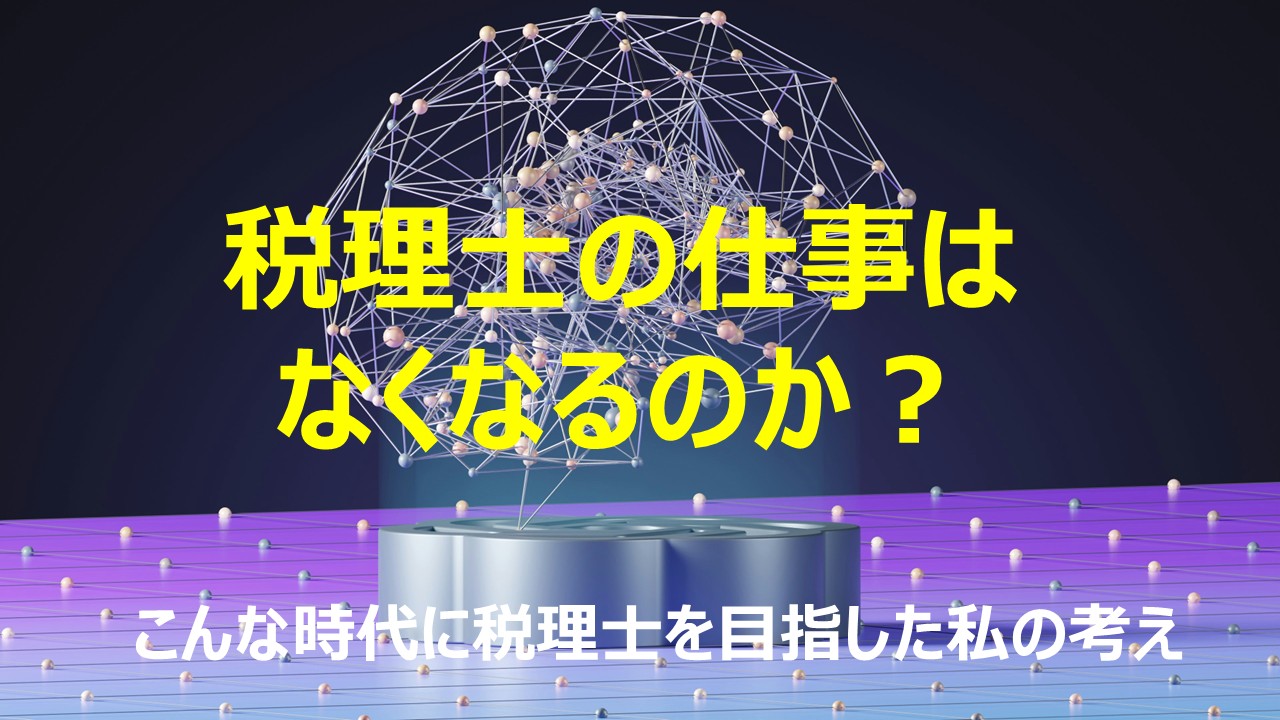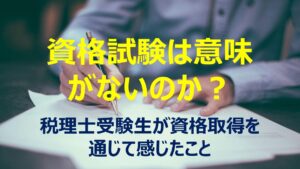AIの普及により無くなる職業の上位に「税理士」がランクインすることは少なくないです。
10年以上前から言われている話ですが、「税理士の仕事はAIに代替されるのか」について、つらつらと書いてみます。
税理士はAIに代替されるのか?
ChatGPTが出現してから、世の中の多くの人が、直接にAIに触る機会が増えました。
私は2023年2月から使っていますが、税理士実務だけでなく、Excelのマクロを組んでもらったり、大学院の論文を要約してもらったり、法律の根拠や解釈を教えてもらったりとあらゆることで助けられてます。
では、メインテーマの「税理士はAIに代替されるのか?」です。
結論、税理士の「存在」を代替することはできません。
ただし、多くの業務はAIで代替可能だと考えています。
※日本の制度が、納税者が税金を計算して申告・納付する方式(申告納税方式)が続くという前提です。
エストニアは国が税金を計算して徴収する方式(賦課課税方式)のため、税理士がいなくなりましたが、日本がそのような制度になることは現実的ではないです。
一般的に税理士の仕事は、「記帳をして、税金を計算して、申告書を作る」だけと考えられているため、真っ先にAIに代替されるイメージがあるのだと思います。
AIに代替される業務
AIで代替される業務は、主に「記録・情報・作業」あたりでしょうか。(5~10年後ぐらいをイメージしています。)
税理士でいえば、「記帳、税務判断を行うための情報収集、申告書作成」などです。
①記帳
クラウド会計の普及により、銀行やクレカの取引データから、自動で仕訳を行うことができます。
精度が完全ではないですが、いずれ多くの部分の記帳はAIがやることでしょう。
現金取引等は完全に0にはなりませんが、OCRで正確に読み取れるようになれば人がやる必要はありません。
チェック業務は税理士の仕事として残る可能性はあります。
納税者がAIを使ってほぼ完璧に仕訳をしていたとしても、それを確認することができないからです。
ただし視野を広げてみると、チェック業務も、大きな間違いはAIで判定(売掛金の回収ができていないことを知らせてくれるなど)できることになり、税理士が行う業務は最終チェックのみと、大幅に減ることは考えられます。
②情報収集
情報収集で使われている方が多いのではないでしょうか。
今までは、わからないことがあったらネットで検索し、いくつもの記事を探すなどして、情報収集をしていました。
しかしAIを使えば、世の中の情報から、我々が知りたい情報を我々が理解しやすいように即座に教えてくれます。
聞き方は工夫する必要がありますが、少なくとも情報収集にかかる時間は大幅に減ったと思います。
③申告書作成
申告書作成については、記帳と同じで入力する値が100%正確であれば、AIは必ず正しい税金の金額を出してくれます。
そのため、記帳や決算作業を100%正確に行うことができれば、完全に自動化できる部分です。(自動化してほしい部分でもあります)
AIができない業務
税務判断
100%正確な記帳がされていれば、税金の計算と申告書の作成はAIですべて完結できるでしょう。
ただし正しい記帳をするためには、税務判断が必要です。
税務判断は、AI時代であっても税理士が最も納税者に貢献できる仕事だと考えています。
AIを使って、「個人事業主 経費の範囲」と打てば、それなりの一般論は答えてくれます。
ただ、税法などの法律はそんな明確に書かれているわけではなく、法律の解釈が必要です。
例えば、法律の中には「社会通念上~」とか「合理的な判断に基づいて~」という表現があります。(常識的な範囲内だったら認めるよとか)
この法律の解釈が必要という部分で、納税者の税務リスクを軽減する(税務署の指摘に対抗できる)判断をすることが税理士の仕事として残ると考えています。
また、正解があるものにはAIは強いですが、個々の事情による感情が影響する部分は弱いです。
例えば法人における、役員報酬をいくらに設定するのか問題。
今後会社がなにに投資していくのか、社長がプライベートでどの程度お金が必要なのか、などによって変わってきます。
相続でもに、最もお得な金額はAIで算出できますが、どのように財産を分割するのかについては人間でなければできません。
さらに、特例の対象となるのかなど、「気づき」が必要な部分については、気づけなければAIに聞くこともできないので、税理士の出番かなと。(税理士側の責任も大きいところです)
責任をもつ
AIは責任を持つことができません。
これが人間とAIの一番違う点かなと個人的には思っています。
法律の解釈は、一般論であれば、AIが教えてくれます。
また、個別の事情についてもAIに入力してあげれば、世の中の裁判例から、今回の事情を当てはめて考えて合理的な判断をしてくれるかもしれません。
ただし、それらの情報を知ったとしても、最後は納税者が判断して申告しなければなりません。(申告納税制度ってやつです)
ここで、納税者が税務リスクを負わないようサポートする(責任を持つ)ことが税理士の仕事として残ると考えています。
税務調査
税務調査対応は、AIには厳しいでしょう。
日本が、国が計算して徴収する方式(賦課課税方式)にならない限り、税務調査はなくなりません。(個人情報の観点からも税務調査自体をAIが行うのは難しいでしょう。)
国税庁では、2021年からAI税務調査が本格的に開始されていますが、あくまでも税務調査に入る企業の選定に導入しています。
税務調査では、税務調査官が企業が正しく申告ができているか、ヒアリングをしながら確認していきます。
ここで、先述した税務判断や責任問題が大切になってきます。
納税者には適切な納税をしてもらい、国税庁からは不当に税金を取られないよう納税者を守るという、中立の立場である税理士の「存在」はなくならないと考えています。
【その他】人は専門家に言われるから安心する
人は専門家に言われるから安心するという側面もあります。
私は、ChatGPTに医者というカテゴリを作って、なにか体の不調があるときはそこに相談するようにしています。
詳細に症状を伝えると、かなり的確な情報をいただけますし、病気の確率や、おすすめの薬なんかも紹介してくれます。
少しの体調不良であれば、それで事足りるのですが、重大な病気かもしれないという不安があるときはどうでしょうか。
お医者さんから「大丈夫です」といってもらったら安心しますよね。
AIで80%の確率で正確な申告書ができたとしても、残り20%の「もしかしたら・・・」という不安を抱えながら、税務調査にビクビクする生活を選ぶのか、専門家から直接「これで大丈夫です」と言ってもらって安心するのか、といったところで、専門家の存在意義があると感じています。
まとめ
税理士がAIに代替される仕事
・会計の記帳業務
・情報収集(経費になるのかなど)
・申告書作成業務
記帳、申告書作成業務は、早い段階でなくなるかもしれません。(なくなってほしいです)
情報収集については、基礎知識の有無やAIをどれだけ使いこなせるかで変わってくると思います。(ネットの検索もうまい人とへたな人がいるように)
税理士がAIに代替されない仕事
・税務判断(税務判断をする過程ではAIを使う)
・責任をとる
・税務調査対応
税理士業界に限らず、いずれホワイトカラーの仕事は9割なくなるかもしれないとも言われています。
そして今もなお、AIの普及により世の中は急激に変化しています。
大切なことは、「この業界はオワコン」「この仕事はなくなる」と考えるのではなく、変化に適応できる力です。
私も、税理士も資格を取ったら食える時代とは思っていないので、「AIに仕事が奪われたくない」と嘆くのではなく、「AIを使う側」の人間でいたいと思います。