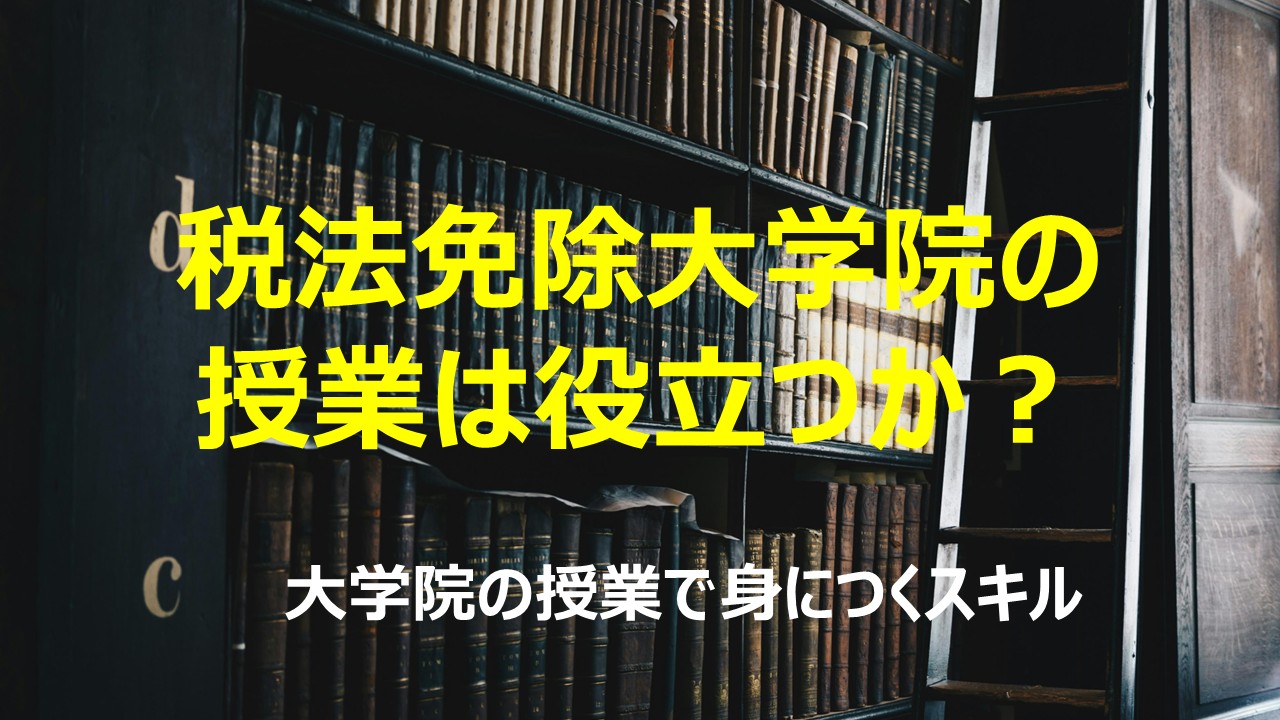税法免除大学院を検討している方の中には、実際に大学院でどんな授業をするのか、実務に役立つのか?と不安の方もいらっしゃると思います。
今回は、現役大学院生の私が、税法免除大学院で「どんなことを学ぶのか」「実務に役立つのか」という視点で解説します。
税法免除大学院の授業は実務で役立つのか?
税法免除大学院の授業が実務で役立つのかについては、「3割程度役立つ」と感じています。
直接役に立つと感じたことはまだ少ないですが、税法の専門家としての教養がつくといったイメージです。
具体的に役に立ったなと思うことは、「税法の解釈について学べたこと」「専門家の知識・意見を聞けたこと」です。
税法の解釈について学べたこと
税理士試験の勉強では、税法の条文は確認しますが、条文が正しいという前提で進んでいきます。
また、法律に書ききれない解釈の部分は、「通達」や「事務運営指針」といった形で国税庁が発しています。
そもそも「通達」や「事務運営指針」は法律ではないですし、国税庁が内部組織に向けて発したものです。
また、法律の解釈の部分は、実際の裁判例を用いて授業が進んでいきます。
第一審、控訴審では国税側が勝訴だったが、最高裁でくつがえって納税者が勝訴した場合、どのような解釈でそのような判決に至ったのか。
様々な裁判例を横断的にみて、こっちでは「独立性」を重視しているけど、こっちの判決は「従属性」を重視している。今回のケースだとどうか。
といった目線で税法に触れていきます。
この解釈の部分は、実務上の「税務判断」や「税務調査対応」などでいつか役に立つかもしれません。
専門家の知識・意見を聞けたこと
例えば消費税の輸出免税についてです。
税理士試験の勉強では、「消費地課税主義」に基づいて、外国へ輸出されるものは消費税をかけないという理屈で学習します。
消費税は消費者が負担しているから、輸出戻し税なんて税はない!と思ってしまいますよね。
受験生だった私も、「たしかにそうだなー」と納得してしまっていました。
ただこれは消費税のできた背景を知ると、実は違うんです。
消費税は、フランスが輸出産業に支援するために「付加価値税(間接税)」という仕組みを作って補助金を渡していたのが始まりです。
日本はこれにならって導入したということが国税庁のHPに書いてあります。
このような、受験勉強では知りえない学者目線の意見や知識に触れることができることは、個人的には勉強になったなと感じるところです。
税法免除大学院で学べること(具体例)
私が通っている税法免除大学院の授業は以下のとおりです。
・租税法(主要な税目すべての基礎知識や歴史・背景・問題点など)
・税法の解釈(毎週裁判例をみていく)
・社会保険や年金など
・会社法
・憲法
・国税庁の組織、裁判の手続きなど
具体的に学んだ内容のメモはこちらで確認できます。
税法免除大学院に行くかどうか検討されている方は、税理士試験1科目にかける時間で、これらの勉強ができると考えてはいかがでしょうか。
税理士試験の勉強とどっちがいいの?に対する私の意見
税理士試験の勉強の方が、体系的にかつ深く学ぶことはできます。(ただし税目ごとに膨大な勉強時間)
大学院の授業は、税法に詳しくなるというより、法律の読み方や解釈の仕方が学べます。
また、主要な税目について、歴史・背景・問題点なども勉強するので、単純に税法の知識がつきます。
というように、アプローチの仕方が全く違うので、単純には比較しずらいです。
私は、教養として大学院の授業を受けてよかったと思っています。(会社法なども学ぶことができました。)
本題とはそれますが、
・税理士試験は1科目に1,000時間+不確実
・大学院の授業は2科目とるのに1,000時間程度(超ざっくり)+確実
と税法免除を考慮すれば、大学院の授業のほうがおトク感はあると個人的には思います。