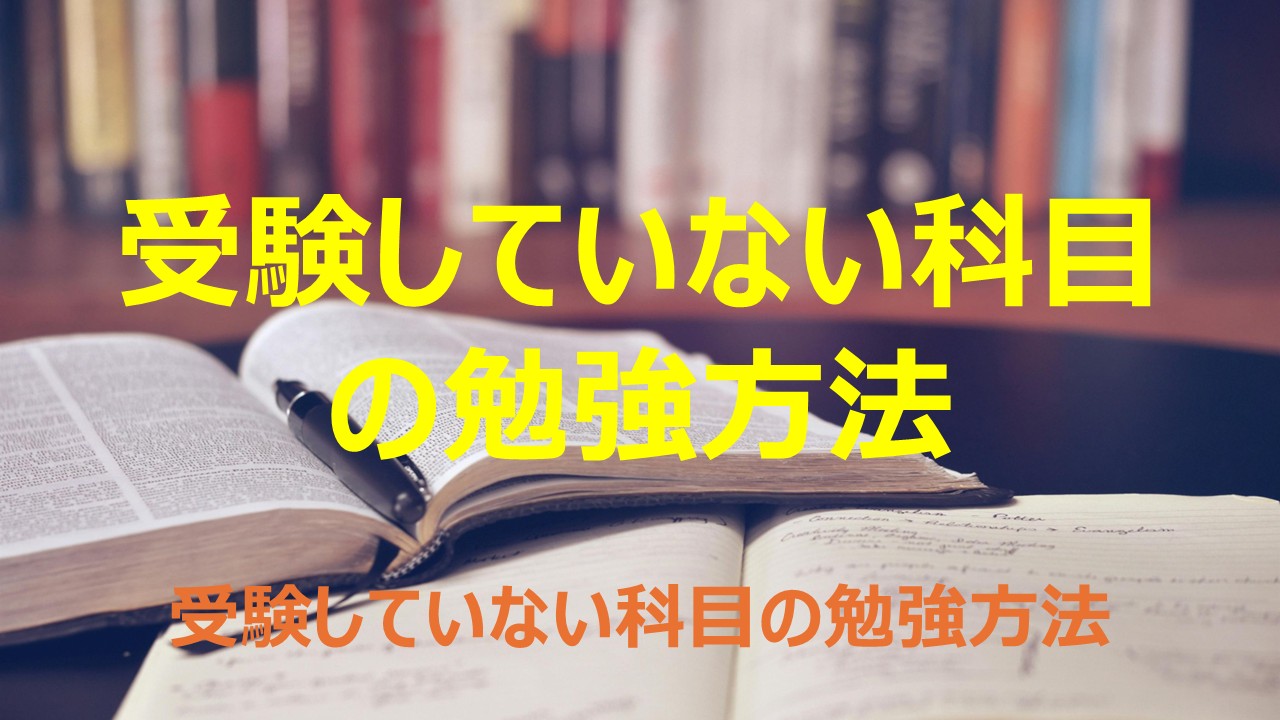ミニ税法受験生や大学院免除の方が悩むポイントのひとつである未受験科目の実務スキル。
いろいろな講座を受講した僕が、未受験科目をどのように勉強をするのがよいかを解説します。
ミニ税法受験生・大学院免除の方が実務スキルをつける方法
実務スキルをつける方法は主に以下の3つがあります。
・受験生向けの講座を受講する
・税理士実務講座を受講する
・仕事の中で書籍やネットで調べながら勉強する
受験生向けの講座を受講する
この方法は、お金・時間に余裕のある方で、なるべく5科目合格者の知識レベルに近づきたい方におすすめです。(特に上場企業などのお客様の支援をしたい方)
受験生向けの講座を受講する方法は、以下の2つのやり方があります。
・受験生と同じように、計算問題・理論暗記をやる方法
・授業のみ受講し、計算問題・理論暗記をやらない方法
受験生と同じように計算問題・理論暗記をやる方法
特に時間に余裕のある方にはおすすめです。
予備校の指示通りに問題を解き、理論暗記もある程度進めることで、5科目合格の方の知識レベルに近づくことができます。
ただし、時間が膨大にかかる上、合格に向けて勉強してる人と比べてどうしてもモチベーションは上がりづらいのが実情です。
タイパを考慮すると、個人的には全範囲を合格レベルまでやるのは、この方法は少しやりすぎな部分があると思うので、自分のやりたい方向(中小企業であれば組織再編はほぼありませんし)と見比べながらどの程度までやるのかを決めるのが良いと思います。
授業のみ受講し、計算問題・理論暗記をやらない方法
僕はこれでした。時間はかけたくないけど、受験生レベルの内容は体系的に知っておきたい人におすすめです。
予備校の授業は一通り見るので、体系的に触れることはできますが、やはり定着はしづらいです。
仕事上で「交際費ってどんなものが入るか知ってる?」と聞かれたときに、なんとなくはわかるけどすぐに答えられないという感じです。
この知識の定着という点では、合格のために勉強してる人にはかなわないので、実務をやりながら鍛え上げる必要があります。
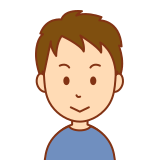
ここだけの話ですが、直前期など演習ばかりの時期は解約して、一部返金してもらうというやり方もあります。
税理士実務講座を受講する
これは、就職していた税理士法人の研修で一通り受講させてもらいました。
自己負担で受ける場合は金額はそれなりにかかりますが、受験生用の講座よりは安価です。
某予備校では、税法入門と申告書作成と別れていますが、可能であればどちらも受講するのが望ましいです。
内容的にはかなり体系的な知識は身につくと思いますので、かなりおすすめです。
受験生用の講座と違う点は、実務講座では、法律の条文を確認しながらの授業ではないというと、組織再編などの一部の応用論点は扱いません。
講義のみでは、税法の条文に沿った体系的理解は足りないので、足りない分は自分で理論サブノートなどで条文を確認するというやり方もよいと思います。
仕事の中で書籍やネットで調べながら勉強する
これは、予備校の講座を受講できない方はしょうがないかもしれませんが、あまりおすすめできません。
1つ1つ調べながらでもできないことはないのですが、やはり効率は悪いと感じます。
僕の場合、未経験・知識なしで実務についたときと、ある程度体系的な知識を入れた後に実務についたときを比べると、頭の入り方がまるで違うと感じています。
同じ事象を調べるときでも、点で把握するのと、大きな幹を理解した上で位置を把握してるのでは、理解力が大きく違うからです。(税理士試験を受験した方なら言わなくてもわかるよと言われそうですが。)
一番のおすすめは「実務講座」、不安な方・上場企業などを支援したい方は「受験生用の講座」
お金に余裕があり、コスパタイパ良く実務スキルをつけたいなら、「実務講座(税法入門・申告書作成)」が一番おすすめです。
ただ税務の専門家としては、ある程度条文を読める必要がありますので、理論サブノートなどを使って自分で条文を確認するのがいいかと。それでも知識に不安な方や、上場企業などを支援したい方は、「受験生用の講座」を受講することをおすすめします。
個人的には、「受験生用の講座」は、中小企業の実務では使わない論点が多すぎるので、中小企業のお客様をメインにしていきたい方は、「実務講座」で十分だと思います。
FPと組み合わせるのもいいかも
僕は、受験生用の講座(法人税・消費税)・実務講座(国税4法)を受講したあと、今はFPの勉強をしています。
FPの勉強内容は、社会保険や年金・金融・生命保険・税法とあり、税法では、所得税・相続税を主に勉強していきます。
そのため、個人や中小企業のお客様対応で使えるスキルとしては結構おすすめです。
まとめ
以下に未受験科目のおすすめの勉強方法をまとめます。
・一番のおすすめは「実務講座(税法入門・申告書作成)」
・不安な方や上場企業などを支援したい方は、「受験生用の講座」
・法人、消費は実務講座、所得、相続はFPという選択肢もあり。
最後までご覧いただきありがとうございました。
少しでも参考になりましたら幸いです。