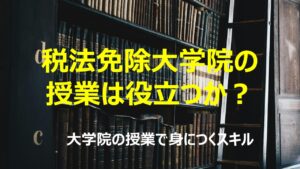税理士になるために、5科目合格を目指すか、大学院免除を選ぶのかは迷いますよね。
今回は、現役大学院生の私が、税法免除大学院のおすすめポイントを解説します。
税理士になれる確率があがる
これが大学院免除の最大のメリットです。
税法科目に合格することは簡単ではありません。
受験する場合は、かなり順調にいっても1年で1科目ずつが限界でしょう。
2科目合格するには2年以上を要します。不合格となれば1年ずつ遅れていきます。
一方大学院免除は、2年で2科目がほぼ確実です。
ちまたでは論文免除が通らない場合もあると耳にしますが、分野を間違えなければ(会計学の論文になってしまっているなど)免除申請が通らないことはほぼないようです。
この確実性という点で、大学院免除は大きなメリットでしょう。
大学院の授業が楽しい
これは、入学してから感じたことです。
税理士試験の受験勉強と、大学院の授業は全く違います。
税理士試験は、税金の正確な計算方法や、法律の条文を暗記する勉強をします。
(税金を手計算したり、条文を暗記することに意義はあるのか・・・)
一方大学院では、法律がどのような経緯でできたのか、実務上の取り扱い(通達など)は、法律の条文上正当性があるのか、といった観点で学んでいきます。
例えば「消費税は輸出戻し税なんじゃないか!大企業への優遇だ!」という話がありますよね。
税理士試験では、「消費地課税主義」として、あくまでも消費者から預かった消費税を事業者が代わりに払っている(間接税)と学ぶので、「輸出戻し税なんてことはない!」と思いますよね。
ただ消費税の歴史的背景を学ぶと、実は違うんですね。
消費税の始まりは、フランスが輸出促進をするために、大企業への補助金として還付する仕組みを「間接税」と定義したのです。
日本の消費税はこれを参考にしています。
というような、税法の専門家の話を聞くことができます。
税法免除大学院で学んでいることについては、以下の記事をご覧ください。
コスパ・タイパがいい
大学院は入学金と学費合わせて、2年間で200万円ほどかかります。1年で100万円です。
この金額をどうとらえるかですね。
受験の場合、予備校代などで1年あたり20万円~30万円といったところでしょうか。
気を付けないといけないのは、受験の場合のこの金額はあくまでも順調に合格した場合です。
税理士になるのが一年遅れることは、この金額以上にダメージが大きいと考えています。
また、金額面で気になる方は、年利が0.05%程度の破格の奨学金制度もあり、ほぼゼロ金利で借りられるので手元資金の心配はありません。(私も借りてます)
今は教育訓練給付で120万円ほどの給付があったり、大学院独自の給付奨学金を実施してる大学院もあるので、しっかり調査すればお金の面はクリアできるかもしれません。
まずは、1年でも早く確実に税理士になる方がいいと個人的には思っています。
税法免除大学院に入学するおすすめタイミング
税法免除大学院に入学するおすすめのタイミングは、会計科目2科目に合格してからです。
実際に会計科目2科目に合格して入学される方が多いです。
会計科目と税法科目は全く別ものなので、会計科目を残したままだと少しモチベーション面で不安かと思います。
また、先ほど述べた通り、大学院の授業は楽しいです。
せっかくの専門家の話を聞ける機会にもかかわらず、税法の基礎知識がないとちょっともったいないかなと感じます。
可能であれば、会計科目2科目持ったうえで、税法の知識を少し勉強(独学でも構いません)してから入学することをおススメします。
ただし、仕事をされている方で、在学中に税法科目1科目に合格するのは、簡単なことではないので、注意してください。