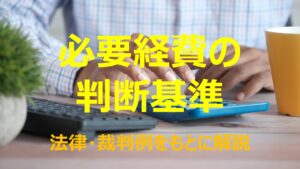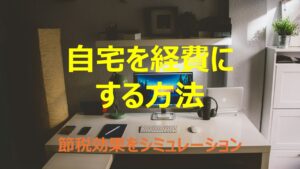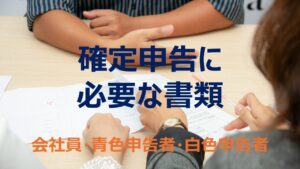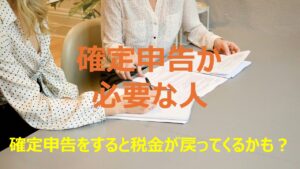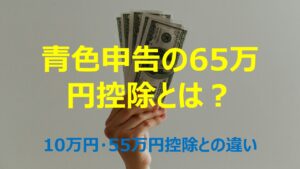給与の計上時・支払い時の仕訳は混乱しやすいですよね。
混乱する原因は、源泉所得税・住民税・社会保険料など性質がちがうものが複雑にからみあうからです。
この記事では、源泉所得税・住民税・社会保険料をそれぞれ分解して、1つ1つ理解できるよう解説をします。
給与の仕訳が難しいと感じる理由
給与の仕訳では、計上時に源泉・住民税を預かる時期と、社会保険料を預かる時期が違うこと、源泉・住民税・社会保険料の納期限が違うため、混乱しやすいと考えられます。
源泉所得税・住民税・社会保険料の基礎知識
この記事では、以下の条件を想定して解説します。
・6月分(6月1日~6月30日)の給与
・支給日は、末締め翌25日払い(7月25日)
・源泉所得税は納付の特例あり
・原則(キチンと)の計算
源泉所得税
給与計上時(6月末)に預かり、翌月10日(7月10日)までに納付する。
納付の特例をする場合1月20日(7~12月分)と7月10日(1~6月分)の年2回納付する。
住民税
給与の計上時(6月末)に預かり、翌月10日(7月10日)までに納付する。
納付の特例はない。
社会保険料
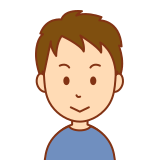
社会保険料が最も複雑なので注意してください。
社会保険料は、会社と従業員が半々で負担(労使折半)するため、それぞれみていきます。
従業員負担分
6月分給与の支払い時(7月25日)に預かり、月末(7月末)に支払う。
会社負担分
給与の計上時(6月末)に未払い計上し、翌月末(7月末)に支払う。
源泉所得税・住民税・社会保険料の仕訳
税金(源泉所得税・住民税)に関する仕訳
●給与計上時(6月末)
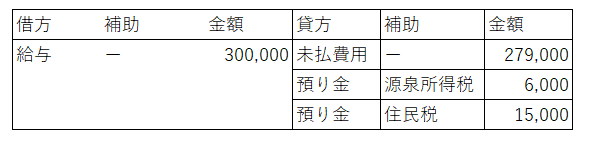
●源泉・住民税を納付するとき(7月10日)
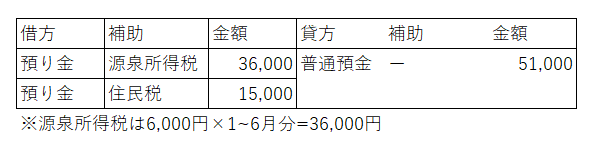
(参考)1月20日と7月10日以外の月は源泉所得税の納付がないため(納付の特例)
以下のようになります。
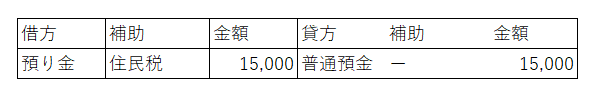
●給与支給時(7月25日)
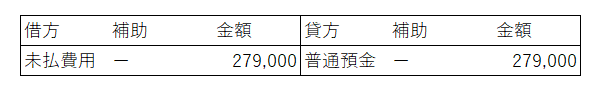
社会保険料に関する仕訳
●給与計上時(6月末)
仕訳なし
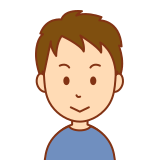
社会保険料だけは、支給時に預かることが多いです。(明確な決まりはないですが)
●給与支給時(7月25日)
復習ですが、社会保険料がなければ以下の仕訳でしたね。
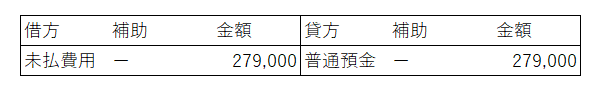
社会保険料は支給時に従業員から預かりますので、以下の仕訳になります。
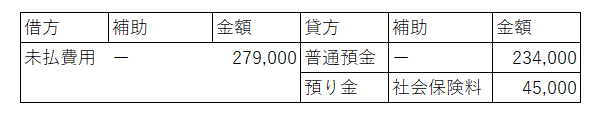
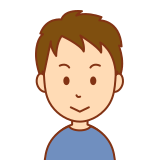
結局いろいろ引かれて従業員の手取りは234,000円ということです。
●社会保険料を納付するとき(7月末)
社会保険料の納期限は、翌月末(6月分給与は7月末)です。
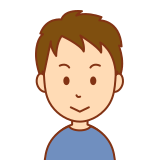
社会保険料は、労使折半でしたね。
従業員負担分と会社負担分の仕訳を分けて記載します。
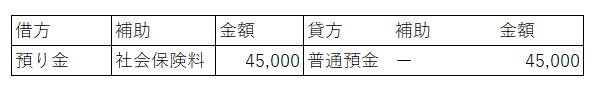
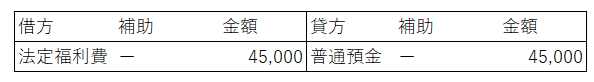
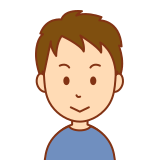
もっと厳密にやる場合、会社負担分の「法定福利費」は、6月末に未払費用計上をして、7月末に未払費用を取り崩す処理をします。
従業員に負担してもらう分は、給与から預かる必要があるため、「預り金」を計上し取り崩す処理をします。
一方会社負担分は、会社が払うだけなので、「預り金」は使わず、納付時に経費計上します。
まとめ
この記事ではキチンとした仕訳の方法を解説しました。
大切なポイントは、以下のとおりです。
・源泉所得税・住民税・社会保険料をひとくくりにせず、それぞれを理解する。
・それぞれを預かる時期、納付する時期を理解する。
・社会保険料は、会社負担分があるので、さらに注意。